
西田剛院長
Nishida Takeshi
内科
自治医科大学医学部卒
・日本内科学会認定内科医
・日本内科学会総合内科専門医
・日本循環器学会専門医
・日本心臓血管インターベンション治療学会認定医
・日本医師会認定産業医
・ICD制度協議会認定インフェクションコントロールドクター
自治医科大学医学部卒
・日本内科学会認定内科医
・日本内科学会総合内科専門医
・日本循環器学会専門医
・日本心臓血管インターベンション治療学会認定医
・日本医師会認定産業医
・ICD制度協議会認定インフェクションコントロールドクター

松尾則行副院長
Matsuo Noriyuki
内科・消化器
岡山大学医学部卒
・医学博士
・日本内科学会認定医
・日本内科学会総合内科専門医
・日本消化器病学会専門医
・日本消化器内視鏡学会専門医
・日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医
岡山大学医学部卒
・医学博士
・日本内科学会認定医
・日本内科学会総合内科専門医
・日本消化器病学会専門医
・日本消化器内視鏡学会専門医
・日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医

土手秀昭副院長
Dote Hideaki
岡山光南病院連携医師
内科
岡山大学医学部卒
・医学博士
・日本外科学会専門医
・日本消化器外科学会専門医
・がん治療認定医
・プライマリ・ケア認定医
・日本リハビリテーション医学会認定臨床医
・日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士
内科
岡山大学医学部卒
・医学博士
・日本外科学会専門医
・日本消化器外科学会専門医
・がん治療認定医
・プライマリ・ケア認定医
・日本リハビリテーション医学会認定臨床医
・日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士

橋本健二副院長
Hashimoto Kenji
岡山光南病院連携医師
内科
兵庫医科大学医学部卒
岡山県岡山市生まれ
・日本内科学会認定医
・日本消化器病学会専門医
・日本消化器内視鏡学会専門医
・日本消化管学会専門医
趣味…スポーツ全般
内科
兵庫医科大学医学部卒
岡山県岡山市生まれ
・日本内科学会認定医
・日本消化器病学会専門医
・日本消化器内視鏡学会専門医
・日本消化管学会専門医
趣味…スポーツ全般
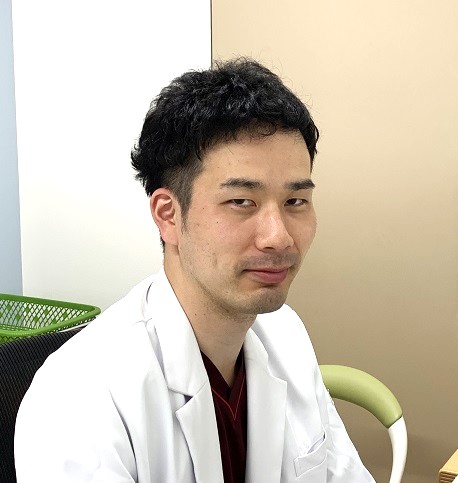
梅田 響医師
Umeda hibiki
岡山光南病院連携医師
内科
岡山大学医学部卒
2024年4月より岡山光南病院勤務
・一般社団法人日本外科学会専門医
・JATECプロバイダー
・緩和ケア研修会修了
内科
岡山大学医学部卒
2024年4月より岡山光南病院勤務
・一般社団法人日本外科学会専門医
・JATECプロバイダー
・緩和ケア研修会修了
寺田整司
Terada Seishi
1990年岡山大学
2025年4月より慈圭病院 精神医学研究所 副所長
こうなんクリニック 老年精神科 非常勤医師
・一般社団法人日本専門医機構 認定精神科専門医
・公益社団法人 日本精神神経学会 認定精神科専門医制度指導医
・一般社団法人日本認知症学会 日本認知症学会専門医
・一般社団法人日本認知症学会 日本認知症学会指導医
・公益社団法人日本老年精神医学会 専門医
・公益社団法人日本老年精神医学会 指導医
2025年4月より慈圭病院 精神医学研究所 副所長
こうなんクリニック 老年精神科 非常勤医師
・一般社団法人日本専門医機構 認定精神科専門医
・公益社団法人 日本精神神経学会 認定精神科専門医制度指導医
・一般社団法人日本認知症学会 日本認知症学会専門医
・一般社団法人日本認知症学会 日本認知症学会指導医
・公益社団法人日本老年精神医学会 専門医
・公益社団法人日本老年精神医学会 指導医
